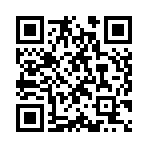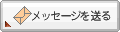2014年07月17日
個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 試製二型機関短銃 電動ガン【突撃!隣のトイガン】

名称:試製二型機関短銃(Wikipedia)
タイプ:電動ガン
メーカー:個人ガンスミスM様
全長:約648mm
重量:約1,8kg(マガジン込み)
発見日:2014年5月3日(土・祝)
発見場所:埼玉県 デザートストーム川越(ウェブサイト)
WWII軍装サバゲ「PHS-4」にて、個人ガンスミスM様がさりげなく試製二型機関短銃の電動ガンをセーフティーエリアで展示していましたのでご紹介します。
※掲載写真では本体にマガジンが入っていますが、撮影時は本体にバッテリー及び残弾が入っていないことを、マガジンにも弾が入っていないことを完全に確認し、なおかつ周りの方々に説明したうえで撮影しています。

左側面です。
試製二型機関短銃が完成したのは昭和12年の1937年ですが、個人的にそのフォルムはその時代にあまり似合わない、何と言いますか、SFチックな印象を受けます。
メカボックスはマイクロメカボックスを使用しています。

右側面です。
スリングスイベルは両方こちら側にあります。
ちなみに日本軍の多くの騎銃系や、九九式短小銃は左側面にスリングスイベルがありますので、そう考えますと位置が逆ですね。
そういえば、一〇〇式機関短銃もフロントのスリングスイベルの位置は右側面にありますが、アレはもし左側面だったら背負う際に色々と不都合がありそう…いえ、ありますね(マガジンを入れたまま背負う必要が出た時にはマガジンが邪魔になりますし、マガジンが入ってなくても出っ張ってるマガジンハウジングが背中に当たって痛そうです…)。

実銃の話ばかりすると肝心な電動ガンのレビューを飛ばしてしまいそうなので、これぐらいにしましょう。
銃口周辺です。
ピンボケしていますね…。
銀色のフチが見えているのはインナーバレルです。
その下にある筒は三十年式銃剣の鍔にある穴に通すための突起です。
さらにその下にあるのが銃剣の柄にある溝に通すレールです。
実物及び複製銃剣を取り付けられるかは確認していませんが、個人ガンスミスM様製の専用銃剣があります(写真にはありません)。
2枚目と3枚目の写真に写っている模造刀身仕様の実物三十年式銃剣を借りて何故試さなかったのかは聞かないでください(爆)

左側面から見たマガジンハウジングとマガジンキャッチです。
マガジンは東京マルイ系MP5用マガジンを使用します。
実銃のマガジン角度を再現するため、マガジンハウジングの位置を斜めにしています。
マガジンキャッチは構造上実銃と同じにすることができないため、オリジナルのマガジンキャッチを搭載していますが、外観を大きく損なわないように必要最低限の大きさでデザインされており、また実用的な構造となっています。
しかし、実際に操作した際はうまくマガジンを外すことができず苦労しました(汗)
個人ガンスミスM様やT氏にバトンタッチした際は何事もなく外れたので、これは単に私の問題でしょう…(笑)

斜め上面から見た状態です。
バレルジャケットの穴も丁寧に空けられています。

斜め後方からです。
バッテリーはバットプレートを外して中に入れます。
対応バッテリーはミニバッテリーでしょうか。

右側から見たレシーバー後方部です。
セレクターらしきものが2つありますが、左側にあるのは射撃セレクター、右にあるのはエアバッファーです。
実銃における射撃セレクターはレバーの位置が上でフルオート、右斜めでセミオート、右でセーフティーになります。
この電動ガンでは実際に機能はしませんがレバーは可動します。
また、実銃では各ポジションに「連(=連射)」「單(=単射)」「止(=セーフティー)」の刻印があります。
写真の状態では「止」ですね。
エアバッファーは試製二型機関短銃の特徴の1つで、実銃ではこれを操作することで連射速度を変更できます。
こちらもこの電動ガンではレバーが可動するだけで、連射速度の変更は機能しませんが、本体内部にある回路を操作することで連射速度を変更することができます。
Wikipediaによりますと、「速度切換え栓」と記されたこの部分を抜き差しすることで調整するそうです。
ちなみにリアサイトの上下調整は可動します。
可動部分はゴムで作られています。
個人ガンスミスM様曰く「全体像が詳しくわかる写真と実銃図面が手元にあるので作ってみた」という理由で開発された試製二型機関短銃の電動ガンですが、現存品が極めて少ない実銃の形状を可能な限り再現し、実際に触って感覚を体感できるのは資料価値としても大きいと思います。
最終的に制式採用の座を勝ち取った一〇〇式機関短銃(後期型)と比較すると、銃身長は1mm違いでほとんど変わりませんが、全長は約200mm短いので構えてみると非常にコンパクトです(現地に個人ガンスミスM様製の一〇〇式機関短銃 前期型の電動ガンがありましたので、より具体的に体感できました)。
ちなみにストックを折り畳んでいない状態で試製二型機関短銃よりさらに全長が短い同世代の短機関銃の1つに、フランス軍の「MAS-38(全長623mm)」があります。
これにて「個人ガンスミスM様製 試製二型機関短銃 電動ガン」のご紹介は以上です。
2014年07月09日
個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2014年3月生産品【突撃!隣のトイガン】

名称:一〇〇式機関短銃 前期型(Wikipedia)
タイプ:電動ガン
メーカー:個人ガンスミスM様
全長:約870mm
重量:不明
発見日:2014年5月3日(土・祝)
発見場所:埼玉県 デザートストーム川越(ウェブサイト)
WWII軍装サバゲ「PHS-4」で知人T氏が個人ガンスミスM様製
以前の所有品から更新したそうです。

去年2013年5月のPHS-2で撮影した個人ガンスミスM様製の2丁です。
上が当時のT氏所有の生産1号機(2012年4月製)、下が私所有の生産2号機(2012年9月製)です。
1号機は元々前期型だったのですが、この時は改修三型仕様になっています。
1号機と2号機でストックの形状が異なりますが、2号機は開発時にモデルガンを採寸用として送りましたので、ディティールアップしました。
この時採寸したデータは後の生産品にも活用されています。

2014年3月生産品(以後、新型と呼称)の左側面です。
ベースは従来の生産品と同じ、AGM製 ステンMk II 電動ガンです。
上記の生産品(以後、旧型と呼称)と比較すると、全体的にスマートな形状になっていますね。
なお、私所有の旧型のレビューはこちらになります。
・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン

銃口とバレルジャケット周辺です。
旧型は全体の寸法の関係で大きめになっていましたが、新型ではよりモデルガン(実銃?)に近い寸法にすることができたため、それに合わせてこちらの寸法も見直されました。
また、それらに合わせて着剣装置など細部もディティールアップしています。
実物及び複製銃剣が着剣できるかは確認していません。
バレルジャケットは塩ビパイプ製からフルメタルに変わっています。

右側面の斜め上から見た状態です。
フロントサイトの形状も見直されています。
ただ、フラッシュハイダーの穴が下部にもあり、合計3つになっているのが気になるところです。
(右側面のフラッシュハイダーの穴の下が突き抜けているのがわかります。実銃は左右両側面の2つです)

真ん中辺りです。
ステンMk IIのメカボの形状の関係でモデルガンより若干高さがありますが、木製ストックの高さを実用強度ギリギリまで下げることに成功したことで、全体的にスマートな形状となりました。
また、旧型ではステンMk IIを流用していたマガジンハウジングを新規で造形したことにより、ストック側面部も再現度が向上しています。

マガジンハウジング周辺を上から見た状態です。
旧型ではステンMk IIを流用していましたが、新型はモデルガンに似せた形状になり、さらにマガジンも東京マルイ系MP5電動ガン用マガジンがそのまま使えるようになりました。
これにより外観におけるステンMk IIの面影は完全になりました。
個人ガンスミスM様は旧型用のバナナマガジンも製作されていますが、市販品をそのまま使えるのは便利ですね。
マガジンハウジングの横にあるマガジンキャッチもしっかり機能します。
写真の右下にある穴はホップアップ調整のイモネジにアクセスするもので、六角レンチを入れて調整します。
使われている素材もフルメタルなので強度は十分あります。

マガジンハウジングの中です。
チャンバー周りはステンMk IIを流用しています。
マガジンキャッチを指で押すと、写真のマガジンハウジングの右下の突起が下がり、マガジンのロックが解除されます。

後方です。
こちらは個人ガンスミスM様によりますと、ほぼモデルガンと同じ寸法とのことです。
バッテリーは旧型から続く仕様でミニバッテリー対応、バットプレートを外してストック内に収納します。
よく見るとトリガーやトリガーガード、リアサイト下のエンドピンの形状も変わっていますね。

右側面です。

ボルト可動部分の溝が再現されています。
パッと見た感じでは塗装で再現しているように見えますが、しっかり溝を作っています。
排莢部分は旧型ではステンMk II流用の関係でメカボの先端が見えていましたが、新型では閉鎖して塗装しています。
(ボルトの位置も閉鎖状態ですので、それに合わせたものと思います)
この周辺の木製ストックの形状も旧型よりモデルガンの形状を再現しています。

リアサイトの形状も変わりました。

旧型では一体成型で無可動でしたが、新型では調整機能が再現されています。
可動部分が増えるのは嬉しいですね。
調整で前後に動かす部分はゴムで作られています。
最初に見た時は意外に思えましたが、ゴム特有の滑り止め効果(?)がありますので、射撃中や移動中の振動で位置がズレることはないと思います。

セレクター(フルオート / セーフティ)です。
ベースとなるステンMk IIは元々トリガーセーフティがなく、旧型1号機は紐で簡易的な、旧型2号機でスイッチで物理的にトリガーをロックする機能が搭載されましたが、新型ではより安全かつ確実にするため電気的にシャットアウトするタイプになりました。
写真の状態はセーフティで、右にスライドすると解除されます。
ちなみに写真にはありませんが、トリガーの通電システムも旧型と同様に、信頼性の高いものに改良されています。
写真で新型のことは知っていましたが、実際に見て触った時は、他の作品同様、個人ガンスミスM様のこだわりが詰まった逸品だと感じました。
PHS-4の時に個人ガンスミスM様より聞いた話ですが、一〇〇式機関短銃のことは気に入っており、まだ作ったことがないという理由で特型(落下傘部隊用の折り畳みストック型)や後期型を作ったり、愛犬のネロ二等兵用にスケールダウンした一〇〇式機関短銃を作ったり、木製ストックの形状をモデルガン同等にすべくマイクロメカボで作ったりと、様々なことに挑戦されています。
「私の一〇〇式機関短銃は旧型」と述べましたが、個人ガンスミスM様やT氏、O氏他、多くの仲間達と出会うきっかけとなった記念品でもありますので、これからも大切に使っていきます。
これにて「個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2014年3月生産品」のご紹介は以上です。
2014年05月06日
個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 特型 電動ガン【突撃!隣のトイガン】

名称:一〇〇式機関短銃 特型(Wikipedia)
タイプ:電動ガン
メーカー:個人ガンスミスM様
全長:約870mm
重量:不明
発見日:2014年5月3日(土・祝)
発見場所:埼玉県 デザートストーム川越(ウェブサイト)
WWII軍装サバゲ「PHS-4」で日本陸軍の義烈空挺隊装備をする知人O氏が
この特型はCAW製のモデルガンではなく、個人ガンスミスM様が開発したフルスクラッチ電動ガンです。
メカボックスは東京マルイ製のマイクロメカボックスを使用し、チャンバーは個人ガンスミスM様が新たに設計、マガジンはMP5用が使用できます。
フルサイズメカボックスよりコンパクトなマイクロメカボックスを使用することで、木製ストックの形状をより実銃に近い形状にすることに成功しています。
特型の特徴といえばストックの折り畳み機能と銃身の脱着機能ですが、個人業者M様はストックの折り畳み機能を再現、銃身の脱着機能も外見のみですがその特徴も再現しています。

銃身周辺です。
特型には前期型で搭載されたフラッシュハイダー(消炎制退器)がないため改修三型のような外観ですが、着剣装置の伸縮機能はなく前期型に準じます。
写真左側、銃身の付け根にあるツマミのようなものは銃身を脱着するための部分です。
電動ガンでこれを再現しようとするとインナーバレルの固定精度や気密などの問題が生じるため外観の再現のみですが、雰囲気はありますね。
ホップアップはチャンバー周りの上に空いている穴にあるイモネジを回して調整します。

ストックを折り畳む基部の右側面です。
蝶番が独特な雰囲気を醸し出しています。

左側面の撮影を忘れてしまいましたが、ストックを伸ばして固定する際は、写真でストック側に伸びている部分を銃左側にある突起に引っ掛けて蝶ネジを締めて固定します。
実銃では「この部分の強度に問題があったのでは?(同じ構造を持つ試製一〇〇式小銃と試製一式小銃は部品精度と共に改善できず試作で断念)」と言われていますが、この電動ガンでは十分実用に耐えられる完成度です。

機関部側のストック断面です。
個人ガンスミスM様の一〇〇式機関短銃はストック後部にバッテリーを入れる構造ですが、特型は折り畳みストックの機能と外観を損なわないためにバッテリーをレシーバー内に収める方法を採用しています。
サイズの小さいマイクロメカボックスを採用したことで実現できた構造ですね。
ちなみにリアサイトは可動します。
一〇〇式機関短銃の電動ガンを積極的に開発している個人ガンスミスM様ですが、折り畳みストックを再現した特型の完成を知った時はとても驚きました。
特に折り畳み機能が可動するのはCAW製モデルガン以来の感動です。
サバゲのゲームスタート時を「降下したところ」という設定にして、折り畳んだストックを伸ばす作業を終わらせてから前線に行く、といった遊び方もできますね。
ストックを折り畳んだ状態は荷物運びの際も便利そうです。
2014年05月05日
アドベン 九六式軽機関銃 電動ガン化カスタム【突撃!隣のトイガン】

名称:九六式軽機関銃(Wikipedia)
メーカー:アドベン(ADVEN、アドベンチャーメイク)
タイプ:電動ガン(カスタム品、オリジナルはBV式ガスガン又はディスプレイモデル)
全長:約1075mm
重量:不明
発見日:2014年5月3日(土・祝)
発見場所:埼玉県 デザートストーム川越(ウェブサイト)
WWII軍装サバゲ「PHS-4」の日本軍側には軽機関銃が数丁ありましたが、その中にアドベン製の九六式軽機関銃を電動ガン化したものがありました。
トイガンとして九六式軽機関銃を発売したのはK.T.W.の電動ガンが最初ではなく、K.T.W.が発売する約10年前にアドベンがモデルアップして発売しています。
アドベンはBV式ガスガンとディスプレイモデルの二種類を発売しており、BV式ガスガンの発売時期はわかりませんが、ディスプレイモデルは1990年のカタログで確認することができます。
(万両というメーカーからもディスプレイモデルが発売されていますが、こちらの発売時期はわかりませんので、当記事ではアドベンが先と記載します)
また、知人がかつて九九式軽機関銃の特徴を持つアドベン製BV式ガスガンを所有していましたが、今となってはその詳細は謎です…。
(見つけたカタログに九九式軽機関銃の記載はありませんでした)
その後2007年頃にディスプレイモデルが発売されるという話題があることから、一時期絶版になった後に再販されたと思われます。

持ち主様から詳細なスペックを聞き忘れてしまいましたので具体的な構造はわかりませんが、同様のカスタム品は他でも見かけます。
そしてそれらの多くはK.T.W.製と異なりフルサイズのメカボックスを搭載していますので、K.T.W.製より連射速度や有効射程、威力などが優れています。
聞き慣れた発射音のしない日本軍の軽機関銃があれば、それは同カスタム品かもしれませんね。
ちなみにアドベン製の九六式軽機関銃のほとんどはキャリングハンドルが少し下向きになっていますので、私はその部分でアドベン製か否かを見た目で判断する基準の一つにしています。

それと、写真を見ている時に気がつきましたが、ストックの付け根にテープが巻かれています。
同カスタム品を持つ知人によると、サバゲで酷使するにはストック付け根の強度が低いそうで(一部パーツを除いて外装のほとんどはABS樹脂製)、その部分の破損は私も何度か見てきました。
このカスタム品はストックの中を削ってバッテリーと配線を中に入れていると思いますので、それによる強度問題が起きているのかもしれません。
2014年05月04日
フルスクラッチ 九九式短小銃 末期型【突撃!隣のトイガン】

名称:九九式短小銃 末期型(Wikipedia)
メーカー:フルスクラッチ
タイプ:エアコッキングガン(ボルトアクション式)
全長:不明(フルサイズ?)
重量:不明
発見日:2014年5月3日(土・祝)
発見場所:埼玉県 デザートストーム川越(ウェブサイト)
WWII軍装サバゲ「PHS-4」にて国民服を着て果敢に戦う日本国民さんが、泣く子も黙る(?)九九式短小銃の末期型を所持していました。

激しい戦闘の中で撮影したので細かいディティールを撮影することはできませんでしたが、末期型の特徴をよく捉えた逸品です。
バットプレートもしっかり木製になっています。
史実では戦局悪化による品質低下の影響で、末期型を鹵獲したり国に持って帰った後に撃とうとしたアメリカ兵達が色々事故を起こし「九九式短小銃は粗悪で危ない」と言わしめた末期型ですが、果たしてこの末期型もそれを再現されているのでしょうか。
(中身はおそらく東京マルイのVSR-10ですね)
2014年04月19日
メーカー不明 自動式拳銃型 8連発火薬鉄砲【突撃!隣のトイガン】

名称:不明
メーカー:不明
タイプ:火薬鉄砲(ダブルアクション式)
全長:不明
重量:不明
発見日:2014年4月12日(土)
発見場所:京都府 チーム「黒騎士中隊」チームフィールド
この日のゲームで、8連発キャップ火薬を使用する火薬鉄砲を持ってきている方がいましたので見せて貰いました。
私の中で8連発火薬鉄砲といえばリボルバー型ですが、この火薬鉄砲は自動拳銃型です。

改めて左側面です。
外装はおそらくM1911がモデルと思います。

右側面です。
こちら側にはネジがないのでスッキリしていますね。
銃口近くでオレンジ色になっている部分がありますが、その周辺は元々オレンジ色になっており、持ち主様が黒色に塗装しました。

刻印は「Made in China」だけです。

驚いたのがこの構造です。
初めて見た時は巻玉火薬鉄砲と思いましたが、「Made in China」の右側にある小さなボタンを押すとスライドの一部が外れ、リボルバー型と同じシリンダーが出てきました。
この構造ならシリンダーを露出させることなく収めることができますね。
火薬を入れる部分は金属製です。

トリガーを引くと、スライドの上にある隙間からハンマーが出てきます。
リボルバー型よりサイズが大きいため握り心地はリボルバー型より良好です。
銃口はシリンダーまで貫通していますので、マズルフラッシュと発射煙も楽しめます。
この火薬鉄砲は残念ながらメーカー名がわからず、販売しているものも見たことがないため、既に絶版になっているものと思われます。
持ち主様は20年ぐらい前に購入したそうで、ゲームで一緒に遊んでいた30代の方も「昔に見たことがある」と記憶されていましたので、少なくとも20数年前、1990年代前半には販売されていたと考えられます。
個人的にこれは物凄く欲しいです。
2014年04月05日
個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ PTRD-41 エアコッキングガン【突撃!隣のトイガン】
名称:PTRD-41 / PTRD-1941(Wikipedia)
タイプ:エアコッキングガン(ボルトアクション式)
メーカー:個人ガンスミスM様
全長:約2,020mm
重量:不明(Ares製 PPSh-41 電動ガンより軽い)
発見日:2014年3月30日(日)
発見場所:京都府 チーム「黒騎士中隊」チームフィールド
この日開催されたWWIIイベント「独ソ戦!演習」でソ連軍に参戦した知人L氏がPTRD-41 対戦車ライフルを持ってきていました。
このPTRD-41は(旧)和室工房様製ではなく、私の一〇〇式機関短銃 前期型の電動ガンの製造元、個人ガンスミスM様製です。
(旧)和室工房様のPTRD-41は2012年頃に少数が生産・発売されましたが、それ以降は生産コストの関係で再生産・再販ができず、2014年4月現在も仮に行う場合はある程度の確実な受注数が取れることが絶対条件となっています。
L氏がPTRD-41に興味を持ったのは完売後のことで、「どうしても欲しい」というL氏の夢を叶えるべく個人ガンスミスM様が今回ご紹介するPTRD-41のエアガンを開発しました。
右側面です。
物干し竿のごとく非常に長いです。
左側面です。
この長さを写真に収めるのはなかなか大変です。
(

ピンと来ない方もいるかもしれませんので、長さの参考写真です。
M4カービンやAK-47で例えると約2.3丁分、M92Fで例えると約9.3丁分、元横綱・曙太郎氏の現役時代の身長で例えるとPTRD-41は約1cm低いです。
銃口から二脚までの銃身です。
マズルブレーキはシンプルですね。
右前斜めから。
フロントサイトとリアサイトは左側にオフセットされています
キャリングハンドル周辺です。
キャリングハンドルの実用は一応可能ですが、強度の関係で過度な負荷は掛けられないとのことです。
バイポットはネジを緩めることで格納、取り外しができます。
レシーバー下部のでっぱりはマガジンを差し込む部分です。
トリガー周辺です。
前述のマガジン周辺同様、VSR-10をベースにしてPTRD-41を開発する際に大きな問題となった部分ですが、外観を大きく崩すことなく最小限のデフォルメで見事に造形されています。
肩当てのクッション部分は使わなくなった鞄を改造して作ったそうです。
左後ろ斜めから。
頬当てのクッション部分も使わなくなった鞄が素材です。
ライブカート式ではないので、装填口はダミーです。
実銃では一発撃つごとにボルトが自動で後退(正常に後退する個体は少なかったそうです)しますが、こちらの機関部はVSR-10なので普通のボルトアクションライフルと同じ仕様です(つまり連射できます)。
ちなみに(旧)和室工房様のPTRD-41はライブカート式で、装填アクションと自動排莢システムを見事に再現しています。
ここまで長いものになりますと持ち運びが大変ですが、二脚から先の銃身はワンタッチで外すことができ(インナーバレルは分割部より前までです)、写真のように二分割できます。
これでさらに二脚を外せば、少し大きめのガンケースに収まるサイズになります。
(
最後に性能ですが、中身はVSR-10なので、VSR-10譲りの高い性能を発揮します。
史実におけるPTRD-41は他の対戦車ライフル同様、対人狙撃(主に戦車から身を出している戦車長)にも使用されていますので、フィールドで見かけた際は狙撃にご注意ください(笑)
実弾(14.5 x 114mm)をまともに食らった人の運命は…想像したくないですね(汗)
2014年03月15日
個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン
今回は私が所有する電動ガン、百式機関短銃 一〇〇式機関短銃 前期型のご紹介です。

名称:一〇〇式機関短銃 前期型(Wikipedia)
タイプ:電動ガン
メーカー:個人ガンスミスM様
全長:約870mm
重量:約2.6kg(マガジン、バッテリー無し状態)
使用バッテリー:ミニ
備考:AGM製 ステンMk II電動ガンを改造

右側面。

左側面。
一〇〇式機関短銃の電動ガンといえば、タナカ製モデルガンを外装ベースとするネモトガンワークス製、東京マルイ製MP7A1をベースにフルスクラッチ(前期型)したオバタヌキ製、東京マルイ製vz.61スコーピオンをベースにフルクラッチ(後期型)したモケイパドック(フェニックス)製、その他個人で製作しているものがありますが、私が所有する一〇〇式機関短銃は個人ガンスミスM様に依頼して2012年夏に完成したワンオフ品です。
タナカ製モデルガンを参考資料として送り、それを元にフルスクラッチで製作して頂きました。
モデルガンのパーツは一切使用していません。

ベースとなったのはAGM製ステンMk IIです。
元々横給弾の構造で、安価に入手できるのでベースにはもってこいです。

銃身周辺です。
バレルジャケットは塩ビパイプ、スリングスイベルは鉄製、それ以外はアルミ鋳造です。
着剣ラグはリアルサイズではないので実物銃剣及び複製品銃剣の着剣はできません。
放熱フィンは再現を省略していますので、ステンMk IIのアウターバレルのまままで。

フロントサイトです。
調整機能はありません。

マガジンハウジング周辺です。
ここはステンMk IIをそのまま使用していますので、全体の中で最もステンMk IIの面影が残っています。
そのため周りの寸法も実銃と変わっているので、バランスを取るため周辺の木製部分と銃身の寸法を実銃より少々大きくしています。
本来はマガジンを抜いてマガジンハウジングを回転しないとホップ調整のイモネジにアクセスできませんでしたが、イモネジの上に穴を開けてすぐ調整できるようにしています。
ホップが可変にならない問題は改善済みです。

レシーバー周辺です。
ステンMk IIのメカボを搭載する関係で、木製ストックは実銃より大きくなっています。
木製ストックはヒノキ、レシーバーは塩ビパイプ、ボルトハンドルはアルミ製で無可動です。

無可動ですが、実銃で分解用金具に当たる部分もあります。

リアサイトはアルミ鋳造の一体形成なので無可動ですが、特徴はしっかり捉えています。

照準を合わすとこんな感じになります。
思っていたより狙いやすいです。

トリガー周りです。
ベースのステンMk IIは構造上トリガーセーフティがありませんが、そのままだと一部のフィールドで持ち込み規制(セーフティへの持ち込み禁止、持ち込む際はバッテリーを外すなど)を受けたり、暴発など安全面の問題も出ますのでトリガーガードの右側にある突起を手前に引くことでトリガーセーフティがかかるようになっています。
ちなみに実銃では奥に押すことでトリガーセーフティがかかりますが、構造の関係で逆になりました。

木製ストック後方です。
スリングスイベルに付けるスリングが欲しいですが、タナカ製の布スリングはとっくの昔に絶版で、あったとしてもプレミア価格です。
でくの房様が革スリングを製造販売していたと思いますが、今も販売しているのでしょうか。

バットプレートはアルミ製です。

外すとバッテリーのコネクタがあります。
使用バッテリーはストック内のスペースの関係でミニバッテリーになります。
バーストコントロールユニットを入れるスペースがあるので、セミオート戦にも対応できます。

マガジンはステンMk IIのものをそのまま使用しますのでストレートマガジンですが、それ故にMP18(MP28)に間違えられることが多いです。
後にバナナマガジンの開発が可能というお話を頂きましたので、将来的にはそちらへ更新する予定です。

トリガーの通電方法は「マイナス切り(プラス側は常に通電状態)」を廃止し、ガンスミスM様特製の通電システムを搭載しています。
これによりスパーク問題や感電の危険など、ここで起因する問題は解決しています。
写真のピントがズレまくってますね…。
また画像はありませんが、主要部品の固定にパテやホットボンドなどは使用せず、ネジを外していくことで簡単に分解できます。
部品の交換も容易ですので、何かがあった際のメンテナンス性も大きいです。
予算などの関係でデフォルメしている場所も色々ありますが、日本軍の秘密兵器(?)として、制圧射撃から乱射突撃まで様々な場面に対応できる逸品です。
WWIIイベントではなかなか使いにくい機種ですが、「日本軍の制式武器で弾が出る一〇〇式機関短銃」というのは大きいですね。
これにて紹介は以上です。


名称:一〇〇式機関短銃 前期型(Wikipedia)
タイプ:電動ガン
メーカー:個人ガンスミスM様
全長:約870mm
重量:約2.6kg(マガジン、バッテリー無し状態)
使用バッテリー:ミニ
備考:AGM製 ステンMk II電動ガンを改造

右側面。

左側面。
一〇〇式機関短銃の電動ガンといえば、タナカ製モデルガンを外装ベースとするネモトガンワークス製、東京マルイ製MP7A1をベースにフルスクラッチ(前期型)したオバタヌキ製、東京マルイ製vz.61スコーピオンをベースにフルクラッチ(後期型)したモケイパドック(フェニックス)製、その他個人で製作しているものがありますが、私が所有する一〇〇式機関短銃は個人ガンスミスM様に依頼して2012年夏に完成したワンオフ品です。
タナカ製モデルガンを参考資料として送り、それを元にフルスクラッチで製作して頂きました。
モデルガンのパーツは一切使用していません。

ベースとなったのはAGM製ステンMk IIです。
元々横給弾の構造で、安価に入手できるのでベースにはもってこいです。

銃身周辺です。
バレルジャケットは塩ビパイプ、スリングスイベルは鉄製、それ以外はアルミ鋳造です。
着剣ラグはリアルサイズではないので実物銃剣及び複製品銃剣の着剣はできません。
放熱フィンは再現を省略していますので、ステンMk IIのアウターバレルのまままで。

フロントサイトです。
調整機能はありません。

マガジンハウジング周辺です。
ここはステンMk IIをそのまま使用していますので、全体の中で最もステンMk IIの面影が残っています。
そのため周りの寸法も実銃と変わっているので、バランスを取るため周辺の木製部分と銃身の寸法を実銃より少々大きくしています。
本来はマガジンを抜いてマガジンハウジングを回転しないとホップ調整のイモネジにアクセスできませんでしたが、イモネジの上に穴を開けてすぐ調整できるようにしています。
ホップが可変にならない問題は改善済みです。

レシーバー周辺です。
ステンMk IIのメカボを搭載する関係で、木製ストックは実銃より大きくなっています。
木製ストックはヒノキ、レシーバーは塩ビパイプ、ボルトハンドルはアルミ製で無可動です。

無可動ですが、実銃で分解用金具に当たる部分もあります。

リアサイトはアルミ鋳造の一体形成なので無可動ですが、特徴はしっかり捉えています。

照準を合わすとこんな感じになります。
思っていたより狙いやすいです。

トリガー周りです。
ベースのステンMk IIは構造上トリガーセーフティがありませんが、そのままだと一部のフィールドで持ち込み規制(セーフティへの持ち込み禁止、持ち込む際はバッテリーを外すなど)を受けたり、暴発など安全面の問題も出ますのでトリガーガードの右側にある突起を手前に引くことでトリガーセーフティがかかるようになっています。
ちなみに実銃では奥に押すことでトリガーセーフティがかかりますが、構造の関係で逆になりました。

木製ストック後方です。
スリングスイベルに付けるスリングが欲しいですが、タナカ製の布スリングはとっくの昔に絶版で、あったとしてもプレミア価格です。
でくの房様が革スリングを製造販売していたと思いますが、今も販売しているのでしょうか。

バットプレートはアルミ製です。

外すとバッテリーのコネクタがあります。
使用バッテリーはストック内のスペースの関係でミニバッテリーになります。
バーストコントロールユニットを入れるスペースがあるので、セミオート戦にも対応できます。

マガジンはステンMk IIのものをそのまま使用しますのでストレートマガジンですが、それ故にMP18(MP28)に間違えられることが多いです。
後にバナナマガジンの開発が可能というお話を頂きましたので、将来的にはそちらへ更新する予定です。

トリガーの通電方法は「マイナス切り(プラス側は常に通電状態)」を廃止し、ガンスミスM様特製の通電システムを搭載しています。
これによりスパーク問題や感電の危険など、ここで起因する問題は解決しています。
写真のピントがズレまくってますね…。
また画像はありませんが、主要部品の固定にパテやホットボンドなどは使用せず、ネジを外していくことで簡単に分解できます。
部品の交換も容易ですので、何かがあった際のメンテナンス性も大きいです。
予算などの関係でデフォルメしている場所も色々ありますが、日本軍の秘密兵器(?)として、制圧射撃から乱射突撃まで様々な場面に対応できる逸品です。
WWIIイベントではなかなか使いにくい機種ですが、「日本軍の制式武器で弾が出る一〇〇式機関短銃」というのは大きいですね。
これにて紹介は以上です。

2014年02月06日
アメリカ製 パンツァーファウスト60m 無可動複製品【突撃!隣のトイガン】

名称:パンツァーファウスト60m(Wikipedia)
タイプ:無可動複製品
メーカー:不明(アメリカ製)
全長:約1045mm
重量:不明
発見日:2014年2月3日(日)
発見場所:京都府 コンバットゾーン京都(ウェブサイト)
【注意】
本ページはウムラウトを含むドイツ語アルファベットを掲載していますので、お使いの環境によっては正しく表示されません。
WWIIイベント「第4回KANSAI WORLD WAR GAME」が雨天予報で延期となり、イベント難民と化した参加予定者の一部がコンバットゾーン京都の通常ゲームへ集結した際に、パンツァーファウスト60mを装備するドイツ兵を見つけました。
モスカートランチャー版パンツァーファウストなど実射ができるものもありますが、こちらのパンツァーファウストは発射機能のない無可動複製品です。
照準を立てる、発射トリガーを押すといったアクションはできます。

弾頭に貼り付けられている説明ラベルです。
書いている内容は多分こんな感じです。
Panzerfaust 60m
(パンツァーファウスト60m)
Vorsicht
(危険)※発射時のバックファイアに対する注意
1. Kopf abnehmen.
(1. 弾頭を外す)
2. Kopf senkrecht halten, Zündladung einsetzen, dass das Papier-Abdeckblatt sichtbar ist.
(2. 弾頭を垂直に保持し、紙のカバーが目視できる状態で点火装置を装填する)
3. Zünder einsetzen m.d. Zündhütchen gegan das papier-Abdeckblatt.
(3. 点火装置のキャップが紙のカバーに面している状態にして信管を差し込む)※「m.d.」は「mid dem」の略
4. Kopf wieder aufstecken.
(4. 弾頭を戻す)
5. Die Pappkappe am Rohrende bleibt beim Abschuss aufgesetzt.
(5. 発射する場合は発射筒の端にある厚紙のカバーを残しておく)※写真のラベルでは赤文字が脱字した「Papkappe」と表記
【参考資料】
・STEINER WW.II ドイツ軍 軍装品 武器類:Panzerfaust 60
・Gi Joe:Dr 70008 "Wolfgang" / Panzerfaust 60

発射筒です。
こちらにも注意書きがありますね。
Vorsicht!
(危険!)
Starker Feuerstrahl!
(強いバックファイア!)
パンツァーファウストに限らず無反動砲の多くは使用の前に周りをよく確認しないとバックファイアで大きな事故に繋がります。
後ろに人がいるのはもちろんのこと、室内や掩蔽壕などでの発射すると射手も非常に危険です。
パンツァーファウスト射撃動画(YouTube)
こうした小道具があると、より一層軍装に「味」を加えることができますね。
2014年01月15日
セミスクラッチ Gew43 電動ガン【突撃!隣のトイガン】

名称:Gew43(Wikipedia)
タイプ:電動ガン
メーカー:セミスクラッチ
全長:約956mm
重量:不明
発見日:2014年1月11日(土)
発見場所:京都府 チーム「黒騎士中隊」チームフィールド
チーム「黒騎士中隊」様の定例会に参加した際にGew43の電動ガンを見つけました。

右側です。
ベースは電動ガンのM14 SOCOMです(メーカーは聞き忘れましたが、東京マルイかCYMAでしょうね)。

左側です。
マガジンポーチは左がGew43用、右がKar98k用で、Gew43を配備された者は通常この2つを装備します。

後方側面です。
ストックはM14 SOCOM純正のストックの上から木粉粘土を盛って作られています。

レシーバー周辺です。
レシーバーはM14 SOCOMのままで、スコープを載せるためのレールがあります。
マガジンの長さの雰囲気を出すため、ショートマガジンを使っています。
セレクターはそのままなので、フルオートでも撃てます。

銃身周辺です。
ストックにある、小さな長方形の隙間も再現されています。
フラッシュハイダーはAK-74のものが付けられています。

バットプレートやスリングスイベルなどはM14 SOCOMの純正品です。

「安価に作れるGew43」のコンセプトで完成したこの作品ですが、ストックの形状やショートマガジンの効果などもあって「Gew43に見える」雰囲気を出しています。
今後の改良でどうなるかが楽しみですね!
ちなみにストック作成時に使用した木粉粘土は「市販でよく見る量で4袋ぐらい」だそうです。