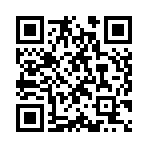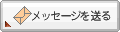2015年04月22日
日本軍 鉄帽の顎紐の結び方例 陸軍式と海軍式(実演有)

今回は日本軍の鉄帽、特に九〇式鉄帽における顎紐の結び方についてです。
日本には伝統的な結び方「兜結び」があり、陸軍でもそれを踏襲した結び方が主流となっていました(兜結び以外にもバリエーションはいくつかあります)。
その兜結びを実演してみようと思います。
用意したのはどこぞのネズミーランドの例のアレが入っている帽子を被る謎の人形です。
私自身を被写体にしてもよかったのですが、撮影セッティングがメンドクサクなったので、飾っていたコレを持ってきました。
やる気のない人形に見えますが、実はコレ、電動式でして、電源を入れるとキュインギュイン音を立てながら目と口が動きます。
まずは鉄帽の中帽となる略帽を後ろに向けて被ります。
帽垂を略帽に装着している場合は後ろ向きだとシュールになりますので正面に向けて被ります。
次は鉄帽の顎紐の調整です。
鉄帽のループに顎紐を通し、写真のような三角形を左右に作ります。
この三角形は耳が通すスペースとなります。
私は鉄帽の縁を基準にして三角形を作っています。
鉄帽を被ります。
左右で垂れている顎紐をそれぞれ顎下を経由して反対方向にある三角形に対し、内側から通します。
左右それぞれの顎紐を折り返し、右頬付近で蝶々結びにします。
画像ではもう一度下顎を経由していますが、唇の下に顎紐を通して結ぶというバリエーションもあります(こちらの方がより伝統的な兜結びになります)。
最後に結び目の輪や余った長さを顎紐に巻きつけるなどで処置して完成です。
もし帽垂を使用している場合は、垂部を顎紐より外側へ出します。
ちなみに、鉄帽のオシャレな被り方として、顎紐のちょうちょ結びの輪を大きくして、最後の処置をせずにそのまま被るといったものがあります(主に将校の間で行われていたそうです)。
以上が陸軍における一般的な結び方です。
「陸軍」という言葉を念押しで使用していますが、実は海軍では陸軍と異なる別の結び方を採用していました。
海軍の鉄帽を所有していませんので陸軍の鉄帽を代用品にして行います。
海軍さんスミマセン・・・。
略帽を被り、顎紐で三角形を作ってから被るというところまでは陸軍と同じです。
ここからが陸軍と異なる部分です。
左右で垂れている顎紐をそれぞれ顎下を経由して反対方向にある三角形に対し、外側から通します(画像は左側です)。
海軍式の三角形部は耳を通すと言うより、顎紐を通す隙間な感じです。
後頭部の中央付近でチョウチョ結びをします。
後は陸軍と同じように顎紐の処置をしますが、処置をせずにそのままの状態で被っている当時の写真や映像もあります。
陸軍のようなオシャレ感覚があったのかはわかりません。
海軍版の完成です。
この結び方は結び目が顔の正面側にないのも特徴ですが、陸軍のように結び目が右頬に来るように顎紐を通している例も確認でき、陸軍同様バリエーションがあります。
実際に陸軍版と海軍版を試してみましたが、固定具合に優劣は感じず、両方共に鉄帽をしっかり固定することができました。
海軍版の結び方には名前があるのでしょうかね・・・?
兜結びと同様に伝統的な結び方の1つなのかと思い、探してみましたがわかりませんでした。
そして、何故陸軍と海軍が異なる結び方になっていたのかも謎です・・・。
「日本軍 鉄帽の顎紐の結び方例 陸軍式と海軍式(実演有)」はこれで以上です。
2015年04月21日
日本陸軍 軍袴 腰紐の結び方例(実演有)
今回は日本軍の軍袴(ズボン)における腰紐の結び方についてです。
当初私は蝶々結びをするものだと思っていましたが、防暑襦袢を着用し始め、腰紐の上から帯革を締めるようになってから「帯革を締めると、軍袴の腰紐の結び目が身体に食い込む」という違和感を感じるようになりました。
「そういう仕様なのだろう」と思い、そのまま年月が過ぎていきましたが、ある日のWWIIイベントで「腰ひもでちょうちょ結びは基本的にしない」という話を聞き、チョウチョ結びでない結び方の1つを教えて頂き、後に同じ結び方を日本陸軍ベテランの証言からも得られました。
それを実演してみようと思います。
使用するのは中田商店製複製のの九八式夏袴、旧ロット品です。
軍袴を穿く前に予め左右の腰紐を後ろと側面のループに通しておくと楽です。

ここからは着装状態で進めます。
ちなみに襦袢はオニヅカ堂製複製です。

左の腰紐を右に、右の腰紐を左に引っ張りつつ、正面で交差させます。
腰紐はねじれないように真っ直ぐ張ります。

さらに側面のループに腰紐を通します。

画像は左腰のループです。
ループを通したところから腰紐を折り返し、ループをまたいで腰紐の下から通します。

余った長さは腰紐に巻きつけて処置します。
右腰も同じように処置します。

位置を調整し、シワを伸ばして完成です(と言いつつシワが残ってますが・・・汗)。
ちょうちょ結びをした状態と比較すると、スッキリした印象ですね。
大きな結び目がありませんので上から帯革を締めても快適です。
さらに、ちょうちょ結びをしている時より帯革をシッカリ締めることができます。
すぐに緩みそうな印象でしたが、しっかり結んでおくと激しい動きをしてもほぼ緩みません。
半袴や略袴、袴下なども同じ結び方でOKだと思います。
という感じで実演してみましたが、例外は付き物でして、腰紐を蝶々結びしている当時の写真もあります。
また、今回実演した結び方以外の結び方もあると思います。
このような話を言い出すとキリがありませんが、私としましては「押さえておくとGOODなポイント」です。
海軍ではどうなっていたのでしょうかね・・・?
腰紐が短く同じ結び方ができない個体も実物(元からか、あるいは戦後民間使用時に加工したか)・複製品共にありますが、その場合は正面で交差させる時にU字で引っ掛けるように180度ねじり、腰紐に巻きつけるという手もあります。
軍の現場における腰紐の短さについては、各自で創意工夫していたものと思われます。
「日本陸軍 軍袴 腰紐の結び方例(実演有)」はこれで以上です。
2015年04月15日
日本陸軍 九九式背嚢(蛸足背嚢) 縛着例(実演有)
今回は「タコ足背嚢」という異名を持つ日本陸軍の背嚢「九九式背嚢」に装備を縛り付ける(縛着)方法の例をご紹介します。
ここ最近、日本軍な人の間では毛皮背嚢や昭五式背嚢などが注目されているようですが、私は九九式背嚢が好みです。
1950年に設立された警察予備隊では九九式背嚢に酷似した(実質改良型?)ものが採用されており、保安隊を経て陸上自衛隊になっても長く使用されてきました。
これが九九式背嚢です(Hiki Shop製複製品)。
中身には気泡緩衝材、プチプチを入れています。
「タコ足背嚢」と呼ばれる理由は、装備を縛着するための紐が多い(16本)ためです。
戦後民間で転用されたタコ足背嚢の中には「邪魔だから紐を切断した」という改造品もあります。
ということでそろそろ本題へ入りましょう。
今回縛着する装備は以下の通りです。
・毛布(実物)
・地下足袋(現行民生品)
・携帯天幕(中田商店製複製)
・九八式小円匙(刃部のみ実物、他中田商店製複製)
・兵式飯盒 再塗装品(現行民生品)
・身体偽装網(メーカー不明複製)
縛着するものは状況によって変わりますので上記の組み合わせは一例です。
それではさっそく縛着してみましょう。
なお、縛着方法についても部隊や個人で差異がありますので一例です。
私は日本軍ベテランの証言や仲間からのアドバイス、当時の写真や映像、イベントで見た例などを基にした組み方で行っています。
勘違いで間違った縛着をしている可能性もありますので、その点はご了承ください。
まずは毛布です。
毛布の巻き方については別記事で紹介していますので、そちらをご覧ください。
【関連記事】
・日本陸軍 毛布の巻き方 九九式背嚢(蛸足背嚢)取付時(http://uag.militaryblog.jp/e577645.html)
背嚢の外周に被せるように毛布を置きます。
左右2ヶ所、上2ヶ所を仮止めで結んでおくと仕上げが楽になります。
また、背嚢の底と毛布の両端を一直線で揃うようにすると綺麗に見えます。
毛布の巻き終わり位置は背嚢の背面、向きは外回りで合わせ、背負った際に見えないようにします。
結び方は団子結びでもOKですが、なるべく背嚢側面の根元で結びます。
また、紐がねじれないように気をつけましょう。
紐を結んだ際にできる毛布のシワはできる限り綺麗に伸ばします。
毛布に限らず、いかにシワなく縛着するかが背嚢を美しく見せるミソです。
毛布の両側面の内、片方には地下足袋を縛着します。
地下足袋の靴底を外側にして毛布の上から縛着します。
なお、写真では左側面に縛着しています(通常は右側面です)。
結び終わったら、両側面共に余った紐を毛布の中に入れます。
背負った際に結び目が見えなければOKです。
入れにくい時は、毛布の巻き終わり位置や結び位置を調整しましょう。
毛布を両側面で固定した状態です。
上の仮止めは解きます。
写真では地下足袋を背嚢に対してよぼ真横に縛着していますが、これに限らず縛着する装備を横に出し過ぎると行軍の際に引っかかり支障が出る可能性があります。
地下足袋の場合の対策としましては、位置を手前寄りにするなどがあります。
次は携帯天幕と九八式小円匙(スコップ)です。
両方共に縛着状態にしています(携帯天幕の畳み方については別の機会で・・・)。
写真の円匙は柄と刃部を結ぶ紐を柄だけに巻きつけていますが、刃部の柄差込口と一緒に巻き付けるとより確実な固定となります。
まずは携帯天幕を乗せます。
位置についてですが、背嚢を立てた状態でイメージすると、毛布の手前にに置く感じです。
また、毛布の時と同様、巻き終わり位置は背面(外回り)にして、正面から見えないようにします。
携帯天幕の上に円匙を乗せ、毛布の時と同じように背嚢背面の目立たない位置で紐を結び、余りの紐を処置します。
天幕にできたシワも伸ばします。
円匙を左側面に縛着する場合もありますが、九九式背嚢では規定上、上に縛着することになっています。
円匙の横付けは昭五式背嚢や昭和十三年制背嚢からの流れを受けているもので、どちらに統制するかは部隊長の判断になります。
また、円匙カバーの上から紐を結んでいますが、(反対側にあるので写真では見えませんが)カバーのループに紐を通すやり方もあります
次は飯盒です。
背嚢の中央に置きます。
背嚢下部にある紐をループに通し、飯盒の吊り手内側から2回持ち手に巻きつけます。
これは飯盒の吊り手を固定するための処置です。
飯盒のループと、背嚢の2つ目のループに紐を通します。
背嚢上面に残っている紐1本を持ってきて結びます。
ここは蝶結びの方がいいでしょう。
飯盒側面からの紐を、同じように吊り手に巻き付け、正面で結びます。
最後は身体偽装網です。
身体偽装網をねじって細くし、天幕と円匙の上から8の字で巻きつけます。
余った長さは、背面の目立たない位置で処置します。
あとは全体を調整して、完成です。
綺麗とは言いがたいですが、以前よりは格段に綺麗に組めたと思っています(当社比)。
なお、仕上げの際に、円匙カバーを通る紐(左側)をカバー側のループを通るようしたので途中で隠れています。
背面はこんな感じです。
雑ですね・・・。
九〇式鉄帽を飯盒に被せて顎紐で固定してみました。
慣れない内は(今もですが)紐結びが面倒と思いますが、実際にタコ足背嚢の使用経験がある陸上自衛隊隊員の証言で「73式背嚢は画期的な新型だった」「タコ足背嚢が嫌なので73式背嚢のPX品(私費の私物品)を購入した」といったものがあります。
また、「背嚢縛着の完成度で兵隊の練度がわかる」という話もあります。

ちなみに2年前、2013年の私はこんな感じです(身体偽装網はありません)。
成長はしていると思います・・・多分・・・(汗)
「日本陸軍 九九式背嚢(蛸足背嚢) 縛着例(実演有)」はこれで以上です。
2015年04月13日
海上自衛隊艦艇見学レポート in 舞鶴基地(京都府):2015年4月5日
4月5日に京都府の舞鶴へ遊びに行った際、停泊している海上自衛隊の艦艇を見学してきました。
この日は艦内見学が無く、外観のみの見学です。
ちなみに海上自衛隊の艦艇を実際に見るのは今回が初めてでしたが、「ひゅうが」と「ましゅう」はホント大きかったです。
「いずも型護衛艦(Wikipedia)」はそれらよりさらに大きいワケですが、一体どんな感じに見えるのでしょうね。
「デカければ負ける(撃沈される)はずがない!」というのも何となくわかったような気がします。
以下に掲載する艦艇写真の解説はすべてWikipediaに丸投げします(手抜き)
【左:あさぎり型護衛艦 1番艦 あさぎり(DD-151)】(Wikipedia)
「あさぎり」は、中期業務見積りに基づく昭和58年度計画3,500トン型護衛艦2222号艦として、石川島播磨重工業東京第1工場で建造され、1985年2月13日起工、1986年9月19日進水、1988年3月17日に就役の後、第2護衛隊群第42護衛隊に編入され、佐世保に配備された。
(撮影時の所属部隊:護衛艦隊第14護衛隊)
【右:はつゆき型護衛艦 9番艦 まつゆき(DD-130)】(Wikipedia)
「まつゆき」は、中期業務見積もりに基づく昭和56年度計画2,900トン護衛艦2218号艦として、石川島播磨重工業東京第1工場で建造され、1983年4月7日起工、1984年10月25日進水、1986年3月19日に就役し、第2護衛隊群に新編された第44護衛隊に「やまゆき」とともに編入され、呉に配備された。
(同所属部隊:護衛艦隊第14護衛隊)
【あさぎり】
【まつゆき】
【はやぶさ型ミサイル艇 1番艦 はやぶさ(PG-824)】(Wikipedia)
「はやぶさ」は、平成11年度計画ミサイル艇824号艇として、三菱重工業下関造船所で建造され、2000年11月9日起工、2001年6月13日進水、2001年10月13日出動公試開始、2002年3月25日に就役の後に第2ミサイル艇隊に配属された。
(同所属部隊:第2ミサイル艇隊)
【あきづき型護衛艦 4番艦 ふゆづき (DD-118)】(Wikipedia)
「ふゆづき」は、中期防衛力整備計画に基づき平成21年度計画5,000トン型護衛艦2247号艦として、三井造船玉野事業所で2011年6月14日に起工し、2012年8月22日に命名されて進水した。
(同所属部隊:第2ミサイル艇隊)
【ふゆづき】
【ひゅうが型護衛艦 1番艦 ひゅうが(DDH-181)】(Wikipedia)
「ひゅうが」は、中期防衛力整備計画(平成13年度)~(平成16年度)に基づく平成16年度計画13,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦2319号艦として、アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド横浜工場で建造され、2006年5月11日に起工し、2007年8月23日進水、2009年3月18日に就役の後に第1護衛隊群第1護衛隊に配属された。
(同所属部隊:第3護衛隊群第3護衛隊)
【ひゅうが】
【左:こんごう型護衛艦 3番艦 みょうこう(DDG-175)】(Wikipedia)
中期防衛力整備計画に基づく平成3年度計画7200トン型護衛艦2315号艦[1]として、三菱重工業長崎造船所で1993年4月8日に起工し、1994年10月5日に進水、1996年3月14日に就役した後、第3護衛隊群第63護衛隊に編入され、舞鶴に配備された。
(同所属部隊:第3護衛隊群第7護衛隊)
【右:ましゅう型補給艦 一番艦 ましゅう(AOE-425)】(Wikipedia)
「ましゅう」は、中期防衛力整備計画に基づく平成12年度計画13,500トン補給艦4015号艦として、三井造船玉野事業所で2002年1月21日起工し、2003年2月5日に進水、2004年3月15日竣工した。
(同所属部隊:第1海上補給隊)
【ましゅう】
【ましゅう】
【ひゅうが艦載リヤカー】
2015年04月12日
日本陸軍 編上靴(アンクルブーツ)の靴紐の通し方(結び方)例(実演有)
今回は日本軍の編上靴における靴紐の通し方についてです。
本記事では「陸軍の5ホール編上靴における一般的な通し方」という前提で進めます。
陸軍と海軍では差異があったのでしょうかね?
それでは、前置きが長くなる前に早速やってみましょう。
用意したのは中田商店製複製の昭五式編上靴です。
靴底の改良がメンドクサクなったのと、ABCマート代用編上靴の使い勝手の良さから箱入り娘状態です。
再現性を考えると中田商店製の方がいいのですが・・・使用するのがもったいないとも思う今日この頃です。
ムーンスター製の複製編上靴、大幅値下げされた時に購入しておけばよかったですねえ・・・アレって再販されるのでしょうか。
話が進まなくなりますので靴紐を通しましょう。
解説は左足用の編上靴で進めます。
まずは1ホール目、両ホール共に表から通します。
2ホール目です。
左1ホールの裏より出る靴紐を右2ホールの裏から通し、さらに左2ホールの表に通します。
右1ホールの裏より出る靴紐は左1ホールの裏から出る靴紐の上を跨ぐ様にします。
3ホール目です。
左2ホールの裏より出る靴紐を右3ホールの裏から通します。
右1ホールの裏より出る靴紐は左3ホールの裏から通しますが、2ホール目の時と同様に重なり部分は上から跨ぐようにします。
4ホール目です。
靴紐を通す方向は両方共に表からですが、右ホールから出る靴紐を上にしてクロスを作ります。
5ホール目です。
今度は裏でクロスを作り、裏から靴紐を通します。
このクロスも右ホールから出る靴紐を上にします。
靴紐をしっかり締めたら、余った分を履き口近くで巻き付けて適度な長さに調整し、正面で結びます。
靴紐の長さは左右対象になるようにしましょう。
左足はこれで完成です。
右足の靴紐は左右反転させて通します。
両方完成です。
私は「4ホール目を表からではなく裏から通す」という勘違いをしていましたが、正しい通し方を教えて貰った際、一緒にいたもう一人も私と同じ勘違いをしていました。
「同じ勘違いをした資料を見て同じ勘違いをしたのだろう」という話になりましたが、間違いを直して靴紐を閉め直した際はよりしっかり結ぶことができ、また緩めるのも楽になりました(クロスのところに指を入れて上に引き上げます)。
今回ご紹介したのはあくまで「数ある例の1つ」ですので、「これ以外はすべて間違い」ということはありません(横線のみ、クロスのみといった例もあるそうです)。
ですが、冒頭で述べたようにこの方法は「一般的な通し方」ですので、再現においては押さえておきたいポイントだと私は思います。
当時の写真からバリエーションを探すのも面白いかもしれませんね。
【関連記事】
・WWIIドイツ軍 アンクルブーツ(編上靴)の靴紐の通し方(結び方)考察(実演有)
「日本陸軍 編上靴(アンクルブーツ)の靴紐の通し方(結び方)例(実演有」はこれで以上です。
2015年04月10日
記録映像で見る第二次世界大戦における小銃(ライフル)の持ち方考察

以前に第二次世界大戦の小銃の持ち方についての考察記事を掲載しましたが、改めてYouTubeでアメリカ・イギリス・ソ連・ドイツ・イタリア・日本の各国軍における例を確認できる映像を別々で見つけることができましたのでご紹介します。
【関連記事】
・1/6 フィギュアで見る第二次世界大戦における小銃(ライフル)の持ち方考察
< アメリカ軍 >
【American Armed Forces - Hell March - World War 2】(YouTube)
< イギリス軍 >
【British Hardcore Hell March WW2】(YouTube)
< ソ連軍 >
【Red Army WWII - Armed Forces of the Soviet Union in Color】(YouTube)
< ドイツ軍 >
【German Army Hell March 】(YouTube)
< イタリア軍 >
【Italian Hell March】(YouTube)
< 日本軍 >
【Japanese Imperial Army Hell March WW2】(YouTube)
< 番外編1:戦国時代 鉄砲隊 再現 >
【2015年 名古屋城春の陣はじまる 火縄銃実演愛知県古銃研究会Network2010】(YouTube)
< 番外編2:戊辰戦争 官軍鉄砲隊 再現 >
【官軍の行進】(YouTube)
< 番外編3:イギリス陸軍 コールドストリームガーズ連隊戦列歩兵 1815年 再現 >
【Coldstream Guards 1815 bayonet charge 】(YouTube)
戦闘中の記録映像を色々見ていくと、発砲より移動を優先にしていると思われる映像ではトレイル・キャリー率が上記各国共通で非常に高いと見受けられます(他の国軍でもおそらく共通することでしょう)。
また、着剣状態の小銃についても、敵との(不意な)遭遇による刺突攻撃の現実味が湧く距離になるまではトレイル・キャリーで移動する(=接近する)方が都合がいいように推察されます。
これらが教育上どうなっていたのかが気になりますね。
「記録映像で見る第二次世界大戦における小銃(ライフル)の持ち方考察」はこれで以上です。