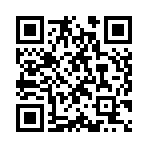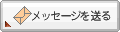2014年12月01日
WWIIドイツ陸軍 迫撃砲運用考察 sGrW34射撃編

今回はドイツ軍の8cm迫撃砲「sGrW34(schwerer Granatwerfer 34)(Wikipedia記事)」の撃ち方についての考察です。
次回のWWIIイベントで迫撃砲部隊に所属することになったのですが、予備知識ゼロでイベント当日を迎えて迫撃砲運用訓練を受けるよりは何かしら頭に叩き込んでおいた方が効率がいいと思い、調べてみることにしました。
一言で運用と言っても一人で運用する訳ではなく、持ち運びその他色々と絡んできますが、ひとまず迫撃砲設置後の射撃場面を主にして見ていこうと思います。
まずは参考資料の選定です。
【参考動画:german mortar team in action】(YouTube)
この動画は海外のドイツ軍な人が行っている迫撃砲運用動画です。
敵の発見から始まり、目標までの距離及び射撃角度の測量、砲兵への指示、射撃までの一連の動作が映っています。
武装親衛隊ですが、多分陸軍とも同じでしょう。
文章系ではスペインで活動するドイツ空軍チーム「FallschirmJäger Regiment 5, I Kompanie(第5降下猟兵連隊第I中隊)」を参考にします。
こちらも空軍での例ですが、こちらに記載されている内容と上記動画で実演している内容がほぼ一致していますので、多分陸軍も同じでしょう、ということで話を進めます。
【参考資料】
FallschirmJäger Regiment 5, I Kompanie (http://www.fjr5.es/) / Ultimas entradas / 8-cm Granatwerfer 34
それでは映像を複数回キャプチャーして製作した静止画を交えつつ流れを見てみましょう。

【1/6】
左から1人目と2人目の人物が観測中です。
左端の人物は測距儀、その隣の人物は砲隊鏡を使用しています。
動画の冒頭では測距儀側が「Achtung. Feindliche Infanterie. Zwohundert Meter.(注意。敵兵発見。200m。)」と報告します。

【2/6】
砲隊鏡側は砲兵側に「Zwohundert Meter.(200m。)」と報告し、規格帽を被る兵はその報告を復唱しながら迫撃砲を調整します。

【3/6】
砲隊鏡側は「Eins Schuss, laden.(単発射撃、装填。)」と命令し、砲弾装填手は砲弾を握って砲口近くまで移動させ、調整側は射撃態勢が整い次第右拳を上げながら「Fertig.(準備完了。)」と報告します。

【4/6】
砲隊鏡側からの「Feuer.(撃て。)」の命令で装填手は砲弾を砲口から落とし射撃、周りは射撃に対する退避体勢を取ります。

【5/6】
射撃完了後、調整側は何かを回していますが、よくわかりません・・・。
おそらく次弾装填に向けての準備操作をしていると思われます。

【6/6】
調整側は操作が終わり次第右拳を上げながら「Fertig.(準備完了。)」と報告します。
以降は「【1/6】」に戻って再射撃に移るか、射撃終了です。
動画の最後では何かを命令していますが、聞き取れずわかりませんでした(動画の流れで予想すると「射撃終了」でしょうか?)。
こんな感じです。
動画を見終わった後の関連動画で別のドイツ軍な人の迫撃砲運用動画がありましたので、それも見てみましょう。
【参考動画:WW2 German Army 8cm Mortar Fire - GrossDeutschland 】(YouTube)
この動画に登場するドイツ陸軍は歩兵師団グロースドイッチュランドですね。
射撃だけではなく、迫撃砲設置作業と撤収作業の映像もあります。
それではこちらの動画もシーン別の静止画にして見てみましょう。

【1/4】
目標観測は右端の下士官が双眼鏡で行っています。
私の聞き取り能力の関係で何メートルと言っているのかはわかりませんが、距離以降の命令は「Twei Schüsse. Feuer frei.(2発射撃。自由に撃て。)」と続いています。
迫撃砲から見て右側の兵は、下士官からの命令を復唱しながら調整します。

【2/4】
調整完了後、迫撃砲から左側の兵(装填手)は砲口近くまで砲弾を持って行き、下士官に「Fertig.(準備完了。)」と報告します。

【3/4】
下士官からの「Los.(行け。)」の合図で射撃し、射撃前に周りは退避体勢を取ります。
2発射撃の命令が出ているので迫撃砲は再装填して2発目を射撃します。
2発目のタイミングについては、「Feuer frei.(自由に撃て。)」となっているので装填側に任せていると思われますが、迅速に2発目を射撃します。

【4/4】
「Feuerpause.(射撃終了)」の命令が出ましたので射撃を終了します。
参考資料ではこの後に迫撃砲及び各使用品の状態確認を行い、問題がある場合は報告することになっているようです。
なお、何らかの理由で射撃を中止する場合は「Stopfen.」と言うそうです。
かなり大雑把なまとめ方になりましたが、部隊や状況などによっては色々変わるでしょうけども、基本はこんな感じだと思います。
迫撃砲部隊に配属することになるとはこれっぽっちも思っていませんでしたので聞いた当初は大いに驚きましたが、よく考えれば、持ち主でもないのにこのような機会に出会うのは貴重ですので、やるからにはカッコよくキメたいところです。
ちなみに予定では迫撃砲は射撃演出だけでなく、実際に(もちろん安全な)模擬弾を敵部隊にガンガン撃ち込むことになっていますので、「直接交戦する友軍歩兵部隊の明暗」にも関わります。
これは緊張しますね(汗)
「WWIIドイツ陸軍 迫撃砲射撃の流れ考察 sGrW34編」はこれで以上です