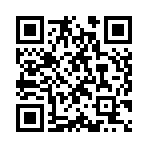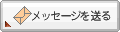2015年01月16日
WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その3(実演有)

今回はガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察の第3回です。
【過去記事】
・WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察
・WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その2(実演有)
トップの画像は2014年12月13日から14日に掛けて和歌山県・バトルランド-1で行われた独ソ戦イベント「ざ・オストフロント」のオフィシャル写真から1枚拝借しトリミングしたものです。
ガスマスクコンテナにガスシートケースが付いているので一見例の違反縛着のように見えますが、よく見ると装具ベルトが使用されていません。
一体どうなっているのか、疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、この装着方法が1942年12月11日に通達された「HM.42, Nr.1100」で改正された装着方法です。
2年前の1940年3月18日通達の「HM.40, Nr.381」に続く、2回目の改正です。

1940年改正の装着方法はケース裏のループの内、上段のみストラップを2回巻きつけるズレ対策が採用されていますが、依然現場からは不評が続いており、装具ベルトを使用してガスマスクコンテナにケースを縛着する規定違反が続きました。
「縛着するのをやめろ!」という命令が何回発令されたのかはわかりませんが、1942年の改正は規定する側が現場の声に折れ、「装具ベルトを使用せずにコンテナへ取り付ける方法」を考え出して再改正を通達したように思えます。
ということで本題ですが、その装着方法とはどのようなものだったのでしょうか。
装着済み状態の写真ではよくわかりませんでしたが、「HM.42, Nr.1100」に記載された実際の内容を確認できる機会がありましたので、それを基に再現してみようと思います。
再現においては前回同様、京都府のWWIIドイツ陸軍歩兵チーム「黒騎士中隊」様の全面協力の基で行いました・・・と言うと大げさ極まりないですが、ガスシートケースを所有しているメンバーさんに協力をお願いしました。
再現にご協力頂き、ありがとうございます。

ということで黒騎士中隊様から頂いた実演写真を基に進めていきます。
まずはガスマスクコンテナのストラップを一旦完全に外し、上記写真のように通します。
解説で使用するストラップには革タブがついていますが、ついていない個体はそのまま通してOKです。
解説は革タブ有りを前提にして進めます。

革タブを使用して右ループにストラップを通す場合の通し方を解説します。
まずは革タブを写真のように通します。

両端の穴にストラップを通します。

先ほど通した穴のすぐ下にある穴にストラップを通します。

ストラップを下に引っ張って完成です。

これで写真と同じ状態になります。

ガスシートケースのループにストラップを通します。
ケースの向きはコンテナの蓋がある方向を上にします。

下のループの通し方はこんな感じです。
次から細かく解説していきます。

革タブを用意します。

写真のように、上下で2回ずつ穴に通します。

コンテナのループに通します。
ウエストベルトに引っ掛ける金具がついたストラップも同じくループに通します。
金具がついたストラップの位置は一番内側にします。

鋲を通す穴を揃え、三重で通して固定します。
写真の状態では二重で、さらに指で差しているところの近くにある穴にも鋲を通します。
複製品の場合、ストラップの生地が分厚いと鋲を通すのに苦労するかもしれません。
写真の複製ストラップは通せなかったため、G3用スリングで使用されているよく似た鋲で代用しています。

これで通し終わりました。

このままでは緩いですので、上部ストラップの位置を調整してストラップをしっかり伸ばします。

これで完成です。
1942年改正の装着方法により、ガスシートケースが直接的に邪魔になることはなくなりましたが、当時の写真でこの装着方法を見つけるのはなかなか困難で、この記事を掲載した時点で明確に判別できる写真を私はまだ見たことがありません。
ほとんどガスマスクコンテナに縛着しています。
STEINER氏の解説には「ループの強度の問題があったせいか、戦場写真でこの装着法を守っている写真をはっきり 確認する事は難しい」と記載されています。
確かにガスマスクコンテナが振れる度にガスシートケースも揺れますし、胸元につけるより大きな振動を受けるでしょうから、振動でループの縫い糸が切れたり摩耗でループそのものが切れたりなどが懸念されます。

【元写真:YouTube動画「HD Historic Stock Footage WWII GERMAN BLITZ BATTLE OF THE BULGE」のキャプチャー】(YouTube)
バルジの戦いで移動中のドイツ軍を映した映像の中で、胸元にガスシートケースを装着する兵士が複数確認できます。
もしかしたら、強度を気にして胸元に装着しているのかもしれません。
その点、装具ベルトの強度は確かなものですので、上官から禁止されない限りそれを使用して縛着する方が信頼性は高いと思います。
という感じで、1942年改正のガスシートケース装着方法の説明は以上になるのですが、1つ気になることがあります。
軍服の上から装着するサスペンダーは規定上肩章の下から通すことになっていますが、当時の戦場写真を見ると規定を守っている姿は少数派です。
これをガスシートケースに置き換えると、規定では胸元、後に装具ベルト無しでガスシートに装着することになっていますが、当時の戦場写真を見ると、特に戦争後期になると装具ベルトでガスマスクコンテナに縛着するケースが増え、1942年改正の装着方法に至っては写真確認が難しいです。

【写真元:海外フォーラムで拾ってきた写真。1935年撮影】
ですが、サスペンダーの場合、規定違反の着装では不都合がある場面においては基本的に全員規定通りサスペンダーを肩章の下から通しています。
これをガスシートケースに置き換えた場合、一体どうなっていたのかが気になります。
サスペンダーのことを考えるとガスシートケースも規定通りに守っていたと思いますが、背面を写した写真はなかなかありませんので確認は難しいです。
また、「ガスシートが支給されていない部隊の整列写真」と思っていたものが、実は「1942年改正の装着方法をしているため、隠れて写っていない」というのもありそうです。
最後に、1942年改正の装着方法を見て思ったことを記します。

【しっかり守っている状態】

【そのまま上から装具ベルトを縛った違反状態】

【注意されそうになったら装具ベルトだけ外して守っている状態へ】

【状況が変わったら再度装具ベルトで縛り違反状態へ】
切り替えが非常に簡単です。
もしかしたら、ガスマスクコンテナに縛着している当時の写真の中にこのパターンがあるのかもしれませんね。
改めまして、実験にご協力頂き、ありがとうございます。
「WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その3(実演有)」はこれで以上です。